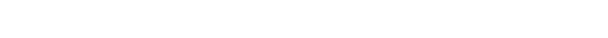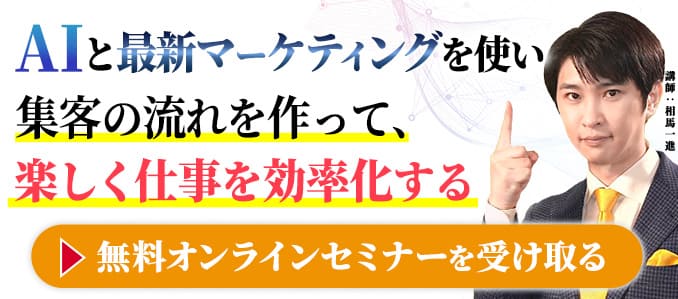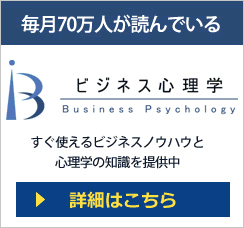こんにちは。
相馬一進(そうまかずゆき)です。
前回から、「このせいでやる気出ない!」という
シリーズ形式の記事を書いています。
第1回目は、
「やる気が長続きしない理由」を
エビデンスに基づいてお伝えしました。
簡単に言うと、「やる気を長続きさせるためには、
やりがいが必須」ということでしたね。
もしまだ読んでいない場合は、
ぜひ前回の記事を読んでみてください。
しかし、この「やりがい」ですが、
マイナスに働く場合もあるんです。
あなたは、その理由がわかりますか?
この理由がわからないと、
「やりがいを感じているのにやる気が出ない」という
矛盾した状態に陥ってしまう可能性があります。
今回は、やりがいのデメリットについて
最新の心理学に基づいて解説します。
やりがいの落とし穴にハマらないためにも、
この記事を必ず最後まで読んでください。
=======================
『 このせいでやる気出ない!(第2回目)』
やりがいがあなたを貶める理由
=======================
「やりがいは、高ければ高い方がいい」と
考えている人は多いです。
あなたもそう考えていませんでしたか?
「やりがいにメリットがあっても、
デメリットなんてない」と。
しかし、残念ながら、
最新の心理学の観点からいうとこれは間違っています。
なぜなら、「やりがいが高すぎるせいで、
ストレスまみれになってしまうことがある」からです。
「やりがいが高すぎるせいで
ストレスまみれになるってどういうこと?」
と思うかもしれません。
そこで、事例をご紹介しましょう。
たとえば、対人サービスを
思い浮かべてみてください。
「対人サービスって何?」と思ったかもしれませんね。
カスタマーサポート、CA、カウンセラーなど、
人が人に直接サー ビスを提供する仕事のことです。
こういった対人サービスは、
やりがいが得られやすいのです。
なぜだと思いますか?
それは、自分の行動によって、
目の前の相手が喜んでくれるかどうかが、
すぐに分かるからです。
確かに、お客さんから
感謝の言葉をもらえたら嬉しいでしょ?
ですので、対人サービスは、
対人サービスでない仕事に比べて、
やりがいが強いわけですね。
それにもかかわらず、なぜ対人サービスでは
ストレスまみれになりやすいのか、わかりますか?
それは、やりがいはあるのですが、
快楽が得にくいからです。
ここでいう快楽って、
どういう意味かイメージできますか?
嬉しい、楽しい、面白い、ホッとする、
癒やされる、リラックスする、ワクワクする、
などのポジティブな感情のことです。
早い話が、一時的な喜びや満足感のことです。
たとえば、快楽が高い行動としては、
おいしいものを食べる、散歩をする、
ゲームをするといった行動です。
イメージできますよね?
さて、アメリカの社会学者の
アーリー・ラッセル・ホックシールドは、
感情労働という言葉を考えました。
ここでいう感情労働とは、
「自分の本当の気持ちとは関係なく、
仕事のためにお客さんに合わせて自分の感情を
コントロールしなければいけない仕事」のことです。
たとえば、あなたがムカついていても、
笑顔で接客をするとか、怒りを抑えて対応するとか、
そういう労働です。
ちょっときつそうでしょ?
対人サービスの場合は、
こういった感情労働が多いため、快楽が得にくいのです。
この意味、わかりますか?
たとえば、カスタマーサポートの場合、
たとえお客さんにムカついても、
ニコニコと笑顔で対応しないといけないじゃないですか。
そんな状態だと、面白くないですよね?
また対人サービスは結果がすぐに出なかったり、
評価が曖昧な場面も多かったりするため、
直接的に達成感や気持ちよさを感じにくいのです。
そのため、対人サービスはやりがいはあるけれど、
仕事そのものがあまり楽しくないということに
なりやすいのです。
すると、ストレスがたまってしまいますよね?
そうなると、ストレスを解消するための行動や
無駄使いが増えてしまいます。
その状態がずっと続くと悲惨です。
最悪、燃え尽き症候群に
なってしまう場合もあります。
わかりましたか?
快楽に比べて、やりがいが高すぎるのは問題なのです。
言い換えると、快楽とやりがいの両方が
高いレベルで満たされるようにする、ということです。
「なんとなく意味は分かるけれど、
具体的にどうすればいいの?」と思うかもしれません。
たとえば、あなたが会社において、
チームメンバーを育成するための
マニュアルを作っていたとします。
そのとき、あなたの感情を
自分で評価してほしいのです。
具体的には、快楽とやりがいを
それぞれ10点満点で評価します。
簡単でしょ?
まず、マニュアルを作ることそのものが
楽しいと感じて、快楽が8点だったとします。
次に、そのマニュアルによって
多くのチームメンバーが成長してくれそうで、
やりがいを感じたとします。
やりがいも8点だったとしましょう。
すると、快楽も8点、
やりがいも8点になります。
そんなに悪くないスコアですよね?
では、他の例も見てみましょう。
たとえば、あなたが
カスタマーサポートの仕事をしているとします。
これも、快楽とやりがいを
それぞれ10点満点で評価します。
そして、快楽が4点、やりがいが7点だったと仮定します。
この場合、やりがいはそこそこ高いものの、
快楽は低いですよね。
では、どうすれば快楽の点数を高くできるでしょうか?
感情労働の場合は、お客さんに共感しすぎると、
こちらも気疲れしてしまいます。
ですので、必要以上に共感しすぎないようにしましょう。
一例として、お客さんに共感するとか
受け止めるのではなく、観察するようにするのです。
すると、メンタルの消耗が減りそうでしょ?
その結果、快楽が少し高くなるかもしれません。
こんな感じで、快楽とやりがいの両方を、
高い点数になるようにするのです。
この考え方を、心理学用語で行動活性化と言います。
読んで字のごとく、
行動を活性化するための心理療法です。
「うーん、いまいちイメージできない」と
感じると思うので、行動活性化について、
まとめてみました。
・快楽もやりがいも高い
→行動活性化。やる気が長続きする。
・快楽は高いが、やりがいは低い
→むなしさを感じやすい。依存のリスク。
・快楽は低いが、やりがいは高い
→ストレスが高い。燃え尽きやすい。
・快楽もやりがいも低い
→無気力。抑うつ。
簡単に言えば、人間は快楽だけでもダメ、
やりがいだけでもダメということです。
快楽とやりがいの両方が高いときに、
私たちのやる気は長続きします。
ここで、弊社のクライアントの事例をご紹介しましょう。
以前、私のところに来た
カウンセラーのクライアントは、
仕事でストレスまみれになっていました。
この理由、わかりますよね?
前述したように、カウンセラーというのは
典型的な対人サービスです。
なので、やりがいが強いものの、
快楽が弱かったのです。
そのため、ストレスまみれになり、
最終的には、燃え尽きてしまったんですね。
この状態、危険でしょ?
そのカウンセラーにとって、
特に大きな問題になっていたのは、
お客さんの感情に巻き込まれてしまっていたことです。
要はお客さんのネガティブな感情を、
自分ももらってしまうということです。
このせいで、快楽が低かったのです。
あなたにも、似た経験があるかもしれません。
そこで私は、
行動活性化の考え方を伝えました。
そして、お客さんと適切な距離感を保ち、
感情的な負担が軽くなるように提案しました。
さらに、仕事から離れて、
リフレッシュ時間を確保するように勧めたのです。
その結果、どうなったと思いますか?
そのカウンセラーは今では、
やりがいだけでなく快楽も強くなりました。
仕事に対するやる気がさらに増えたのです。
そのおかげで、私がコンサルして5年後くらいには、
ビジネスの売上も8倍くらいになったそうです。
すごいですよね。
私からすると、そのカウンセラーが
ビジネスで結果を出してくれたのはもちろん嬉しいです。
ですが、もっと嬉しいのは、
そのカウンセラーが本当に楽しそうに
ビジネスをしていることです。
その姿を見てると、コンサルタントとして
冥利に尽きる思いだなぁと感じます。
さて、自己啓発やスピリチュアルの講師で、
こういった最新の心理学の知識を伝えている人は
皆無だと思います。
あなたも、そんな講師、見たことないでしょ?
たしかに、
「やりがいを感じられる行動をしましょう」
みたいなこと「だけ」を教えている人はいます。
しかし、「快楽が低い場合、やりがいは害である」
ことは前述したとおりです。
そういうことを知らないのでしょう。
私にいわせれば、
「快楽がなく、やりがいだけの行動」は
「ドレッシング抜きの野菜サラダ」のようなものです。
確かにドレッシング抜きの野菜サラダは、
健康的で体に良いかもしれません。
でも、美味しくないでしょ?
なので、食べるのがストレスになりますよね。
そして、食べ続ければ、
いずれ燃え尽きてしまいます。
だから、自己啓発とかスピリチュアルの
古い理論を盲信すると、ストレスまみれになったり、
燃え尽きてしまったりするのです。
古い理論だけに、盲点だらけなんですよね。
さて、ここまで読んであなたはどう感じましたか?
行動活性化について、
少しは興味を持っていただけたのではないでしょうか。
ですので、いよいよ次回は
行動活性化の3ステップについてお伝えしますね。
=======================
以上、「このせいでやる気出ない!」の
第2回目でした。
もし、あなたがやる気で悩んでいるのであれば、
ぜひ次回の記事も見逃さないようにしてください。