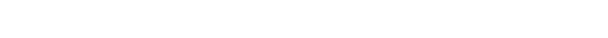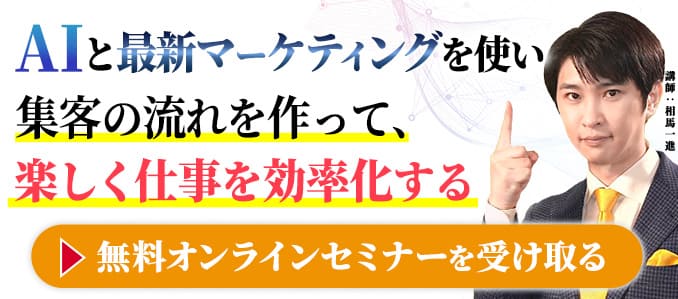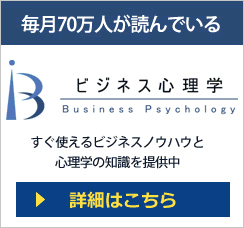こんにちは。
相馬一進(そうまかずゆき)です。
今回からの記事は、
「高IQほどハマるマーケティングの落とし穴」
と題して、シリーズ形式でお伝えします。
ですので、「自分は平均以上にIQが高そうだ」
という人はぜひ読んでください。
もちろんIQに自信のない人も、必見の内容です。
なぜ、平均以上にIQが高い人ほど
マーケティングの落とし穴にハマるのかわかりますか?
答えは、そういう人ほどマーケティングの理論を
たくさん知っているからです。
実は、マーケティングの理論には、
広まった後で間違いと証明されたものも多いのです。
しかし、「間違いだった」という事実は、
なかなか広まりません。
そのため、間違った理論を信じてしまい
売上を下げている人がたくさんいるんですね。
そのような人の多くは、IQが平均以上に高い人です。
実際、私自身も高IQと呼ばれる部類ですが
過去には、このマーケティングの落とし穴に
ハマったことがあります。
だからこそ私は、海外の大学の論文などをもとに
マーケティングの真実を検証してきました。
この記事では、エビデンスに基づいて
ちまたのマーケティングの常識を
覆すような内容を紹介します。
もちろん、定説を覆すだけではなく、
再現性があるマーケティングの戦略も
お伝えするので、ぜひ最後まで読んでください。
=======================
『高IQほどハマるマーケティングの落とし穴
(第1回目)』
牛丼の吉野家と松屋の客層は違う?
=======================
あなたは「ターゲティング」って、
できると思いますか?
ここでいうターゲティングとは、
特定のお客さんに狙いを定めて、
その人に商品を買ってもらうことです。
この質問をすると、
平均以上のIQを持つ人はこう答えることが多いです。
「ターゲティングができる」とか、
「ターゲティングをすべきだ」と。
一方、IQが低めの人はターゲティングという言葉を
そもそも知らないことが多いんですよね。
あなたも、ターゲティングは可能だと思いましたか?
でも、エビデンスに基づいて言えば
実はターゲティングはできません。
「えっ、何でできないの?」
「実際ターゲティングって、
世の中で使われているじゃないですか」
と、感じたかもしれませんね。
そういう感想を持った時点で、
あなたはすでに落とし穴にハマっています。
その理由と解決策を説明していきますね。
正確にお伝えするために、
まずターゲティングにまつわる
重要な2つのクイズに答えてみてください。
クイズ1:
牛丼チェーンの吉野家と松屋の客層は
どれくらい違いますか?
クイズ2:
コカ・コーラとペプシの客層はどれくらい違いますか?
この2つのクイズ、どちらも返答に困りませんか?
だって、どちらのクイズも、
両社の客層はほとんど同じように感じるからです。
しいて言えば、クイズ1は
吉野家は何となく男性が多い一方で、
松屋は家族連れが多いイメージかもしれません。
テーブル席の数が松屋の方が多いからですね。
でもまあ、吉野家も松屋も客層はほぼ同じに見えます。
そして、クイズ2のコーラとペプシも
客層の違いはよくわかりませんよね?
もしこのように感じたとしたら、
あなたの直感は正しいです。
つまり、真実はこうです。
牛丼チェーンの業界だろうと、
炭酸飲料の業界だろうと、
「同業種の客層はほぼ同じになる」。
こう言うと、「何を当たり前のことを
言っているんだ?」と思うかもしれません。
ですが、平均以上のIQを持つ人は
「ターゲティングができる」と思っているんです。
たとえば、「うちの商品は30代の男性に
買ってもらおう」みたいに決めたら
実際に買ってもらえると思っているわけですね。
しかしこれは、大昔のマーケティングの理論です。
つまり、理論のアップデートができておらず、
落とし穴にハマっているということです。
「何を根拠にそう言っているの?」
と思うかもしれませんね。
そこで、南オーストラリア大学の研究結果を
ご紹介しましょう。
英語ですが、詳しく知りたい場合は読んでみてください。
Ehrenberg-Bass Institute Academic Paper
https://sponsors.marketingscience.info/wp-content/uploads/sites/2/_pda/ac_pub/2018/11/Some-Practical-and-Theoretical-Difficulties-of-Target-Marketing.pdf
この研究では、コカ・コーラの購入客は
ペプシコーラもまた購入していることを、
データの点から説明しました。
つまり、「お客さんは、同業種の違う商品も
たくさん購入する」のです。
この法則は、
エビデンスに基づいたマーケティングの世界では
「購買重複の法則」と呼ばれています。
この法則を知らないマーケターって、
かなり多いんですよね。
あなたは、知っていましたか?
さらには、この論文では
次のような事例がいくつも紹介されています。
企業側はターゲティングしたつもりだけれど、
全然ターゲティングできていなかった事例です。
たとえば、キットカットで有名な
ネスレという食品メーカーがありますよね?
このネスレは、海外では「ヨーキー」という
チョコレートバーを販売しています。
知っていますか?
私も知らなかったのですが、
この論文を読んで初めて知りました(笑)。
ともかく、ヨーキーを売る際に
「これは女の子向けではありません」と明記したのです。
その結果、女の子向けではないと
書いてあるにもかかわらず、
なんと購入者の47%が女の子でした。
ほら、ターゲティングできてないでしょ!
平均以上のIQの人は、
ターゲティングをした「つもり」になっていますが
実際はできていません。
だって「吉野家と松屋」も、
「コカ・コーラとペプシ・コーラ」も
客層はほぼ同じでしたよね?
ということは、特定の客層を狙って
集客するなんてことはほぼできないことを意味しています。
経営コンサルタントの中には、
「ターゲティングをして棲み分けをすれば、
同業他社と戦わずにすむ」という人もいます。
しかし、エビデンスに反していて間違いなんです。
実際には戦わないことなんてできません。
つまり、あなたの商品も、同業種の他の商品と
お客さんの頭の中で比べられてしまっているのです。
たとえ、あなたが
ターゲティングをしてもしなくても、です。
ここまで読んで、あなたはこう思うかもしれません。
「もしターゲティングができないなら、
どうすればいいの?」と。
その方法は簡単で、
ターゲティングで絞り込むのではなく
むしろ客層を広げるのです。
そして、あなたも同業他社と同じような客層を
集めればいいのです。
では、何をすれば客層は広がるのでしょうか?
やることはとてもシンプルで、次の3ステップです。
1. 同業他社が獲得できているが、
あなたが獲得できていない客層を見つける
2. 同業他社の集客や販売や商品の中で、
どの部分がその獲得できていない客層に
響いているのかを考える
3. その部分において、同業他社がやっていることを
素直にマネする
具体例をあげて説明しますね。
たとえば、牛丼チェーンの「すき家」を
考えてみましょう。
すき家は吉野家よりも、
家族客が多いです。
なぜでしょうか?
その理由は3つあります。
【店舗設計】
テーブル席の比率が高く、
ボックス席まである店舗もある
【メニュー構成】
お子様牛丼セットなど家族向けメニューが充実
【CM戦略】
アニメ『クレヨンしんちゃん』の一家が
すき家で食事するCMなど
こういった理由で、
すき家は家族客を増やすことができました。
そして結果はどうでしょう?
データを見ると、すき家(ゼンショー)は
吉野家や松屋の2倍以上の売上になっています。
牛丼大手3社の売上高の推移
https://gyokai-search.com/3-gyudon.html#jump2
「えっ! そんなに違うの!?」
って思いませんか?
吉野家や松屋は、家族客を取り込まない限り
すき家に追いつくのは難しいでしょう。
このように、同業他社のマネをしないと
本来上げられるであろう売上を、
上げ損なってしまうのです。
なぜなら、同業他社が獲得できている客層は
あなたも獲得できるはずだからです。
「それって、大企業の例じゃないの?
中小企業や個人事業主でも同じことが言えるの?」
と思うかもしれません。
そこで、私のクライアントの事例をご紹介しますね。
私のクライアントに、
インド占星術を教える先生がいました。
インド占星術は、簡単に言えば
中国の四柱推命とか西洋占星術に似た
インドに伝わる占いの一つです。
その先生は最初、「インド占星術だから
西洋占星術や四柱推命とは違う客層になる」と
思っていました。
しかし、私は
「占星術という業種は同じなので、客層は似ている」
と考えました。
そこで、「西洋占星術や四柱推命のビジネスの
やり方をマネしましょう」とアドバイスしました。
具体的には、商品構成や価格設定、集客方法などです。
その結果、1ヶ月で月商30万円、
1年で月商100万円を達成し、
念願の海の近くへの引っ越しも実現しました。
このように、マニアックに見える商品でも
客層を広げることで売上は上がるのです。
今回は、ターゲティングに焦点を当てて
一般的なマーケティングの落とし穴を解説しました。
しかし、ターゲティングの他にも、
多くの人が信じている「間違った理論」は
いくつも存在します。
次回は、「差別化」のウソについて解説しますね。
=======================
以上、「高IQほどハマるマーケティングの落とし穴」
の第1回目でした。
次回も、マーケティングの常識を
覆すような内容をお伝えするので、
ぜひ見逃さないようにしてください。